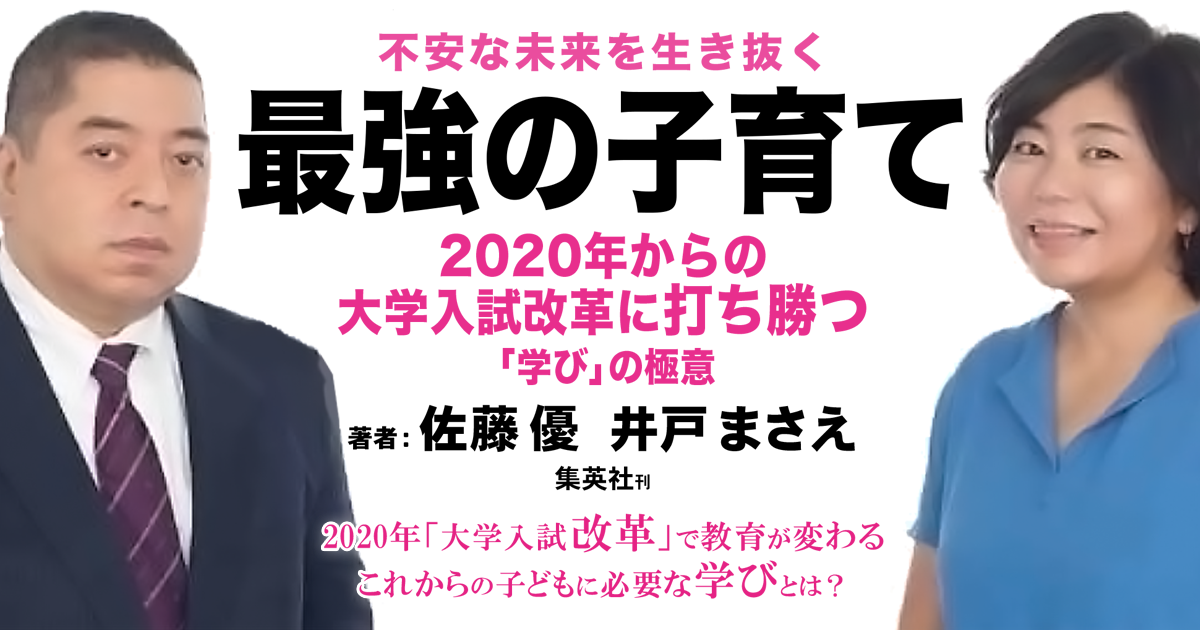
大学入試センター試験が、2020年1月の実施を最後に廃止され、2020年(21年1月実施)から「大学入学共通テスト」に移行します。
ご紹介する『不安な未来を生き抜く 最強の子育て』は、大学入試改革に打ち勝つ「学びの極意」をズバリ教授する、改めて注目したい一冊です。
著者は、「知の巨人」こと佐藤優氏と元衆議院議員でジャーナリストの井戸まさえ氏。
大学院で神学を専攻した異色の外交官だった佐藤氏に、5児の母であり教育や子育ての現場に詳しい井戸氏が問いかける形で、次々と剛速球が投げ込まれていきます。
大学入試改革はOSの大転換
教育や子育てを考える際、入試は避けて通れないテーマです。多くの親・子どもの最大の関心事だからです。
しかし、これまでは、あえて入試を避けるかのように、「ゆとり教育」とか「生きる力を育む教育」といった抽象的な議論ばかりでした。
ところが、今回の新学習指導要領で、従来の知識偏重型から「思考、表現力、判断などを問う」方向に、大学入試改革が連動して変わってきます。大学入試から変えていこうとしているのです。
2017年5月、「大学入学共通テスト 記述式問題のモデル問題例」が発表されました。数学の問題例では、「公園に設置する銅像を最も見えやすくするために、広場の広さはどのくらいあればいいか」を考えさせる問題となっています。
国語では、駐車場使用契約書を題材にしています。また、英語では、段階的に「英検」や「TOEIC」などの外部試験に移行するとのことです。(2021年1月の共通テストでは見送られましたが)
自らの力で思考し、判断し、(英語を含めて)表現することが問われるわけです。これについて佐藤氏はこう述べています。
もし、この改革がうまくいけば、ざっくりいって10年後に社会人になる連中は、新しい、要するにバージョンアップしたOSになるわけです。
まもなく小学生からプログラミングを授業に取り入れるようになるし、文系でもプログラミングとか、アルゴリズムとかがわかる子たちが普通に出てくる。
そうすると、今の大学生というのは、最後の古いOSで、つまりWindows98みたいなものを使わされているようなもの。だから、もう少したつとアプリが動かなくなるかもしれない。(中略)
今の大学生、それから今30代くらいの人たちまでは、教育改革など自分には関係ないと思わずに、危機感を持ったほうがいい。
入試で問われる「再現力」
受験勉強には弊害もあれば効用もあります。気力体力ともに充実した子ども時代に、問答無用で無理矢理、暗記したことは、必ず後になって役立ちます。
新テストで「思考力、判断力、表現力」を重視するといっても、豊富な知識が予め頭にインプットされていれば、より深い思考と判断ができるわけですし、語彙が豊富なほど豊かな表現が可能になるはずです。
大学入試改革で、その受験勉強のやり方も変わっていくのでしょうか。著者の2人はこう言います。
佐藤: これまでもこれからも、高校までの学力というのは主に、「教科書に書いてあることを1時間半とか2時間という制限された時間の中で筆記で再現する能力」が問われているんですね。 (中略)
まずは教科書に標準的な日本語で書かれている内容を正確に記憶に定着させて再現する。
このスキルは仕事においても絶対に必要なことですから。マニュアル人間はダメと一方で言うけれど、そもそも仕事ってマニュアルを読んで覚えて実行することが基本でしょう。そのための訓練にもなるわけです。
井戸: 結局、学校教育・大学受験で培うべき重要なことは、「きちんと記憶して、それを自分なりに再現する能力」ということですね。
要は基本は変わらないということです。
英語も、「聞く」「話す」にも力点が置かれるようになりますが、これも今まで通り「読む」をおろそかにはできません。佐藤氏も言っています。
「読む力」を、「書く力」「聞く力」「話す力」が超えることは絶対にないということ。
読んで理解できないことは書けないし、話せないし、聞いてもわからない。だから読むことを選考させないといけないわけです。
↓↓関連記事もあわせてどうぞ
塾で学校を補完
今回の教育改革は大きな実験でもあります。学校現場にその影響がどう出てくるのかは、ふたを開けてみないとわかりません。
そうした不透明ななか、子を持つ親としては、どう立ち向かっていけばいいのでしょうか。本書では言葉を濁さずに言い切っています。
佐藤: 今の一般的な学校教育だけでは無理ですよね。現実的に考えれば。
井戸: そうすると家庭教育でやるしかないというわけですか。
佐藤: いや、家庭ではむずかしい。やっぱり受験産業でしょう。(中略)例えば、高校教師は別に英語4技能(読む、聞く、書く、話す)受験の指導がこなせなくても失職はしないわけです。
でも塾や予備校の講師は、もし4技能受験のノウハウ、タクティクスがないと入試に合格しないということになったら、これはもう必死に習得するでしょう。
井戸: その違いということですね。
佐藤: その違い。生活がかかってますからね。だから、そこの部分は受験産業で補完していけばいいんです。もはや公立の小中高というのは、いじめが起きないこと、基本的な生活習慣を身につける場所、と割り切るぐらいの気持ちで。
井戸: そこまで割り切りますか・・・。
多少の違和感を感じる方もいるでしょう。
勉強は、極論すれば、一人でもできます。学校教育では、一人では身につかないこと、例えば、集団生活のルールや先輩・後輩の上下関係とかを肌で覚えることとか、学校行事を通して、みんなと一緒になって1つの目標を成し遂げた達成感を経験すること、を期待していますので、両者のやりとりに私は違和感はありません。
ただ、塾や予備校で補完といっても、先立つものが気にかかります。
教育費の集中と選択
佐藤: バレエとピアノと習字と英語と水泳と。そんなにいくつもやって、ものになるはずがないんです。そこで集中と選択が出来るかどうかというのは親の力です。
親の力というのも、ここで言っているのは見極める力と、経済的な感性。経済力そのものではなくて、自分の経済を正確に把握する力のこと。
井戸: 結局どこに集中的にお金をかけるかということですね。中高でいい教育を受けさせたいのか。小学校なのか、大学なのか。
佐藤: 一般論として早い方がいい。早いうち、プレスクール段階のところで集中して机に向かう訓練さえできていれば、後は比較的順調にいきますよ。それが確立していないところで、あとから矯正を、ということになるときついんです。これはあとになればなるほど大変になりますからね。
その時期を過ぎた子ども持つ私としては、「遅かったかも?」と心配になります(笑)。
ほかにも本書の内容は多岐にわたります。親の世代というより、むしろ現役の高校生や大学生が読めば、大いに刺激を受けるのではないかと思います。以下、目次で内容を紹介しておきます。
第1章 戦後最大級の大学入試改革を迎え撃て
第2章 「4技能」時代に勝てる語学力の身につけ方
第3章 大学受験改革後、価値ある大学に進むには?
第4章 卒業後の人生を分ける 大学での学び方の極意
第5章 佐藤優が直伝!学力をグンと伸ばす方法
第6章 教育とお金の問題
第7章 あなたの子どもはAI時代に生き残れるか
第8章 自立できる子ども・できない子ども
今回ご紹介した本はこちら↓
読後感
井戸: 親が子に自分を重ねている間は、子どもからその重しはとれない。子どもに期待するばかりではなく、私自身が新しい教育システムの中で本気で勉強したいな、という気持ちが湧いてきました。
佐藤: ぜひ、勉強は続けてください。やってみると、子どもに言うほど簡単ではないとわかりますからね。新しい時代の学びを体感するのも、大事な経験だと思います。
よし、子どもの中学入学を機に、英語と数学の学び直しをやってみよう。もはやOSのバージョンアップは無理でも、マイナーチェンジくらいはできるかもしれませんから。
以上、『AI時代に負けないために改めて注目したい一冊 『不安な未来を生き抜く 最強の子育て』』でした。
